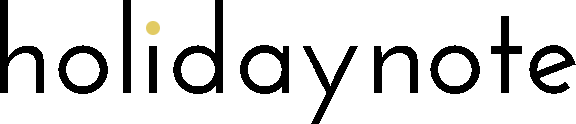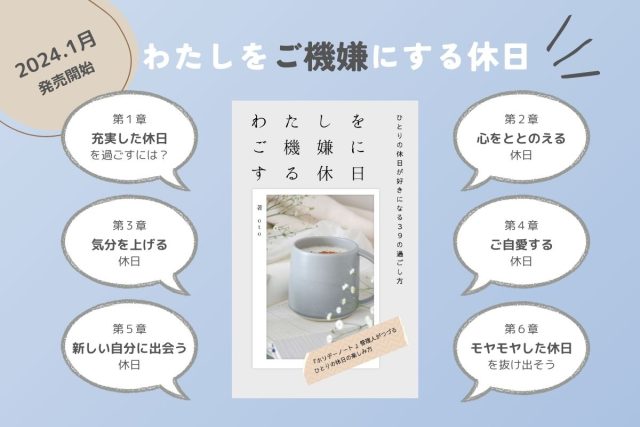小さいながらもとても美しく、趣のある庭園があると聞き、足を運んだのは板橋区にある「水車公園」。日本庭園も公園の一部のようだけれど、水車があるエリアとは道を挟み、独立する形で日本庭園が広がっていました。
水車と水田がある水車公園

東武東上線「下赤塚駅」より徒歩15分、東京メトロ副都心線「地下鉄赤塚駅」より徒歩17分ほどの場所に広がる「水車公園」。名前のとおり、園内には管理事務所にもなっている水車小屋がありました。

小屋の中には管理人さんがいて、「こんにちは〜」と声をかけながら入ると、水車の仕組みがわかる展示がありました。ゆっくりと回る様子を眺めていると、なんだか気持ちが穏やかになります。

水車のすぐそばには水田。9月に訪れたので、稲が実っていました。手作り感あふれるかかしも置かれ、ほっこりします。
水車と水田は、かつて板橋区でも行われていた水田稲作の様子を再現したものだそう。ここだけ、時が止まったような雰囲気が漂います。
まるで我が庭のように日本庭園を散歩

庭園の出入口には、瓦屋根を従えた門。小さな庭園ながら立派な佇まいの門に期待が膨らみます。さっそく「お邪魔しま〜す」とばかりに園内へ。

訪れたのが9月上旬ということで、ピンク色の百日紅(さるすべり)がきれいに咲いていました。青い空によく映えます。

池は「心字池」。文字通り、「心」という文字をかたどった池です。

園内からまわりのマンションなどが見えることから、そう大きくないのは想像がつくと思いますが、面積は約1,200平方メートルです。
けれど、このこぢんまりとした規模だからこそ、まるで自分の庭のような感覚に。この日は、園内には私しかいなかったこともあり、なおさら我が庭感が高まりました。
茶室「徳水亭」のまわりを見学

庭園は、茶室「徳水亭」の周りの茶庭と池を中心とした浄土式庭園だそう。浄土式庭園とは平安時代後期に広まった庭園様式で、「極楽浄土の世界」を池や建物で表現したもの。
ちなみに茶室は、事前予約(有料)で、お茶のお稽古や茶会に利用できるようです。

水琴窟を発見!水を注いでみると、けっこうはっきりと音が聞こえました。金属音のような澄んだ音色に癒されて、思わず2回もその音を楽しんでしまいました。

書院露地にはつくばい。つくばいとは、茶室に入る前に手や口を清めるために設けられた手水鉢。

茶室の縁側に腰掛けて、しばし休憩。縁側からは目の前にたくさんの緑が広がる景色を眺めることができます。

腰掛待合(こしかけまちあい)とは、茶室に入る前に客人が腰をかけ、亭主から呼ばれるのを静かに待つための場所。小さな東屋のように造られていて、雨や日差しをしのげる工夫もあります。
枯山水も美しくてうっとり

茶室の出入口前には、枯山水も広がっています。9個の石が置かれていますが、これは仏教の世界観にある「須弥山(しゅみせん)」を表現したもの。

須弥山とは、世界の中心にそびえると考えられてきた神聖な山のこと。そのまわりには8つの山と8つの海があるとされ、須弥山とあわせて「九山八海(くせんはっかい)」と呼ばれてきました。
日本庭園の枯山水では、石を組み合わせてこの須弥山やそのまわりの世界を表現することがあり、限られた庭の中にダイナミックなスケールをぎゅっと詰め込んでいるのです。

枯山水があまりに美しくて、気づいたら、いろんな角度から何枚も写真を撮影していました。
小さいながらも見どころがいっぱいの庭園だった

私が訪れたのはまだ暑さが残る日でした。緑が美しく清々しい散歩が楽しめましたが、こちらの庭園はきっと、葉っぱが少ない季節でも、日本の侘び寂びを感じる美しさが楽しめるような気がします。葉っぱが赤や茶に染まる頃に、また訪れたいなぁと思いました。
小さいながらも、枯山水や心字池、サルスベリの花、茶室など見どころが多く、思いのほか長い時間を過ごした「水車小屋・日本庭園」。手入れの行き届いた園内は、ただ歩いているだけでも心が癒される時間でした。
住所・アクセス/関連サイト
東京都板橋区四葉1-16
東武東上線「下赤塚駅」より徒歩15分
東京メトロ副都心線「地下鉄赤塚駅」より徒歩17分
都営三田線「高島平駅」より徒歩25分