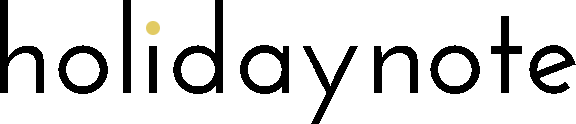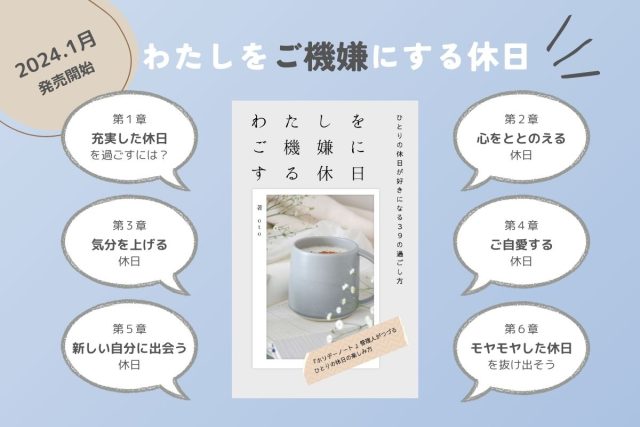町田市にある「小野路(おのじ)」をご存知でしょうか?朝日新聞社と森林文化協会が2008年に選定した「にほんの里100選」に、東京で唯一選ばれている町です。
少しだけ涼しくなった9月のある平日、小野路散策に繰り出しました。
私は小田急線「鶴川駅」からバスに乗り「小野神社前」で下車。バス停の近くにある「小野路宿里山交流館」を拠点に散策を楽しみました。
小野路宿里山交流館で腹ごしらえ

これから約5キロの、アップダウンのある道のりを歩くため、散策前に「小野路宿里山交流館」で腹ごしらえをすることにしました。
江戸時代に甲州街道と八王子道を結ぶ交通の要衝として栄えた宿場町「小野路宿」において、旅籠のひとつだった「角屋(かどや)」を改修したもので、今は観光交流の拠点として整備されています。

施設の中心となる主屋には、小野路産の野菜や果物、加工品が並ぶ「物産・直売コーナー」、散策に役立つ地図やバス時刻表をそろえた「情報コーナー」、そして食事やお茶を楽しみながら休憩できる「交流スペース」が設けられています。
木材には柿渋に墨を混ぜた塗料が使われ、主屋全体に古き良き風合いが漂います。

お食事は11時からいただけます。私がいただいたのは「小野路うどん(650円)」と「里山コロッケ(150円)」。といっても、お食事メニューはこの2つのみ。
小野路産の地粉を100%使用したうどんは、いわゆるうどんとは少し違って、どちらかというとお蕎麦に近い食感。温かいつゆには豚肉やごぼうも入っていて、見た目以上に満足感がありました。
里山コロッケは、ゴロっとしたじゃがいもが入っている素朴なタイプ。里山らしい、なんだか懐かしい味わいです。
里山の風景が広がる小野路散策へLet’s Go!

小野路宿里山交流館を後にして最初に出会ったのは、すぐ隣にある「小野神社」。今回は前を通っただけですが、小野路宿のシンボルのひとつとなっています。

神社を通り過ぎたところで、バッグから小野路宿里山交流館で手に入れた「散策ガイドマップ」を取り出し、いよいよ散策スタート。この地図は、痒いところまで手が届くような、ものすごく親切な地図です。トイレの場所や道しるべとなるポイント、見どころなどが丁寧に記載されています。

最初に辿りついたのは「万松寺谷戸(ばんしょうじやと)」。谷戸とは、丘にぐるりと囲まれた谷あいの低地のことを指します。田んぼや小川がつくられ、まわりには雑木林が広がるなど、里山らしい風景が残る場所です。
東京からどこか遠くまで旅行に訪れたような、とてものどかな景色が広がります。

谷戸内には民有地も含まれるため、案内板を確認し、通行可能なルートに沿って見学します。

万松寺谷戸を見学したあと、ガイドマップの散策ルートによると、次は「六地蔵」に出会えるとのこと。ワクワクしながら歩いていくと、ほどなくして案内どおりに六地蔵の姿が現れました。
仏教の六道輪廻(六つの世界=地獄・餓鬼・畜生・阿修羅・人間・天上)」の思想に基づき、江戸時代後期に作られたそうですが、数えてみると7体あります。

ゆるやかな坂道を登りながら、だんだん見晴らしがよくなっていくのを感じます。

坂道をえんやこらと登り、ひたすら進んでいくと「萩生田牧場」の牛舎がありました。黒毛和牛を子牛の時期から出荷まで育てており、防疫上の理由から普段は中に入ることはできませんが、外から牛舎を眺めることができます。
艶やかな黒毛をまとった立派な牛が2頭!1頭はこちらに顔を向けていて、その様子がなんだか可愛らしく、しばらく眺めてしまいました。

誰にも出会うことなく、緑が生い茂る中を歩きたどり着いたのは、小山田一族が築いたとされる平山城の跡「小野路城址」。主郭跡には「八雲神社」が建ち、スサノオと牛頭天王が祀られています。

ひたすら山道を歩いていると、「本当にこの道であっているのかなぁ」と不安になる瞬間がやってきます。
しかしガイドマップには、道しるべとなるポイントが随所に記載されており、なんと送電線の鉄塔のマークまで描かれています。
実際に鉄塔が目の前に現れると、「よし、合ってる!」と思わず嬉しくなり、そんなわけで、普段なら撮影しないであろう鉄塔をパシャリと撮影。

鉄塔を確認したあとは、次のポイントとなる「竹林」まで、こうした細い道を歩いてきます。

「竹林はまだかなぁ」とドキドキしながら歩いていくと、目の前にスッと現れる竹林!「お、合った!」とホッとする瞬間がやっぱり嬉しく、こうした小さな発見も、小野路散策ならではの楽しさのひとつです。

竹林を抜けて険しい階段を下ると、「奈良ばい谷戸」があります。散策ルートの中で、ここだけ、車通りや人通りのある道に面しており、「はぁ、やっと人に会えた〜!」とちょっとホッとする場所です。
私が訪れた9月には、稲穂がたわわに実り、黄金色に染まった田んぼの風景が迎えてくれました。

奈良ばい谷戸は、もともと荒れていた田畑やや林地を、地元の市民とNPOが協力して再生してきた場所です。東西に500~800メートルほど続いています。
「はぁ〜」と思いっきり深呼吸をしたくなる、清々しい里山の景色です。

藁葺きの屋根が目を引く素朴な小屋が建っていました。これは、かつてこの地域で生産されていた「黒川炭」を焼いていた伝統的な施設を再現・保存したものです。

散策ルートには番号が振られた道標が点在していて、ガイドマップと連動しているので、それを頼りに進んでいけます。本当に、何から何まで親切ですね……。
番号は1〜13までありますが、私は途中で何度か見落としていて、いきなり数字が飛んだりしました。
さてここは「11」チェックポイント。次は「12」と記された浅間神社へ向かいます。距離はおよそ400メートル。どんな景色が待っているのか楽しみです。

浅間神社へ向かう道中、きれいな一本道を通ります。

階段を上り、小高い丘の上にひっそりと鎮座する「浅間神社」に到着しました。御祭神は、富士山を象徴する女神・木花咲耶姫命(このはなさくやひめのみこと)です。
境内には青々とした芝生が広がり、清々しい空気に包まれます。冬の季節には葉が落ちて、木々の間から富士山を望めることもあるそうです。

狛犬も鎮座しています。

狛犬の先は参道になっており、草が生い茂るなかに鳥居が佇んでいるのが見えました。神秘的な雰囲気ですね。ガイドマップの散策ルートに沿って歩くと、この鳥居をくぐることはありません。

浅間神社を後にして歩みを進めると、最後の「13」チェックポイントを見つけました。このあたりには標高はまぁまぁ高そうですが、畑や家もあり、人がいる気配を感じます。
「小野路バス停」と書かれている矢印のほうへ歩いていくと、「小野路宿里山交流館」があるバス通りに到着します。道標には、ここからは520メートルと書かれています。

距離にして約5キロの道のりを歩き終え、ようやくバス通りに戻ってきました。山道を上ったり下ったりしながらの、2時間ほどの散策。本当にお疲れさまでした!
このバス通りは「小野路宿通り」と呼ばれる、かつては旅籠や商家が並んでいた場所です。

今も黒塀の家並みや町割りに往時の面影が残ります。景観を守るために電柱も少ないです。せせらぎが心地よく流れており、散策の疲れも癒やされていくようです。
kitchenとまりぎでひと休み

当初は、再び「小野路宿里山交流館」に戻って、コーヒーを飲みながらバスを待ちつつひと休みしようかと思っていましたが、せっかくなので、違う場所でひと休みすることに。
小野路宿通りにある「ヨリドコロ」は、古民家を改装した地域の複合施設です。

その一つとしてカフェ「kitchenとまりぎ」があります。栄養バランスの取れたランチが味わえる「なっちゃんの社食屋さん」や、こだわりコーヒーを提供する「Ramita Coffee」など、日替わりで店主が変わるスタイルが特徴です。

こじんまりとした店内は、明るい日差しがたっぷり入ります。木のぬくもりあふれるデザインで、山小屋に遊びに来たよう。

私が訪れた日は、自家焙煎珈琲が楽しめる「Ramita Coffee」。アイスコーヒーで喉を潤しました。
おわりに

都心からもアクセスしやすい町田市に、こんなにのどかな風景が広がる場所があるなんて、驚いてしまいました。
がっつりハイキングを楽しみたい場合は、「小野路宿里山交流館」を拠点にして散策するのがおすすめ。里山の風景を楽しめればいいという場合は、「扇橋」バス停で降りて、「奈良ばい谷戸」を訪れるだけでも十分に癒やされるのではないでしょうか。
ただ、個人的には、「小野路宿里山交流館」のうどんがとても美味しかったので、ぜひ味わっていただきたいなと思いますし、宿場町の雰囲気も味わえて、ちょっとした旅行気分も楽しめます。
住所・アクセス/関連サイト
東京都町田市小野路町888-1
小田急線「町田駅」または「鶴川駅」よりバスで「小野神社前」下車すぐ
小田急線・京王線「京王多摩センター駅」よりバスで「小野神社前」下車すぐ