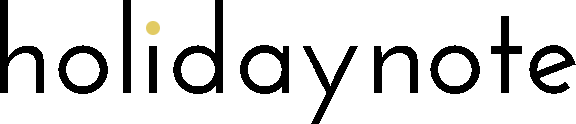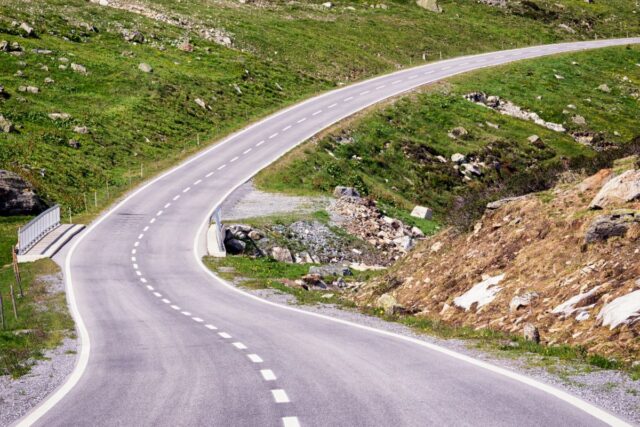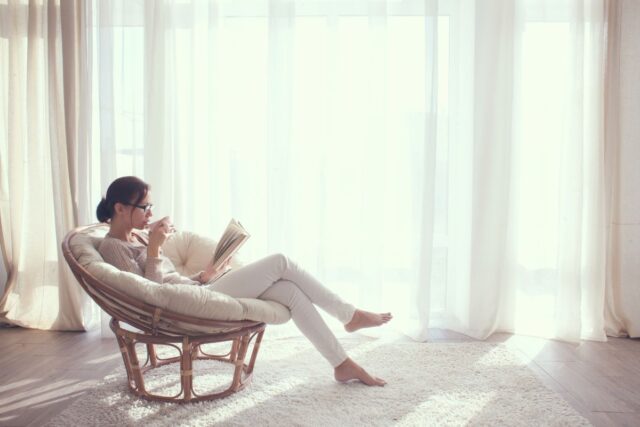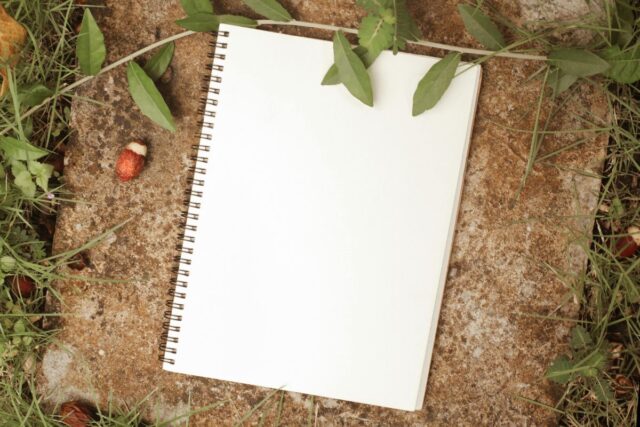私から見ても圧倒的に実力があるように思える人が、「まったく自信がないんです」とつぶやくのを聞いたとき、昔の私は驚きました。「えっ、こんなすごい人でも自信がないの?」「自信を持っていいのに」と。
けれど、書くことを続けるうちに、まだまだ試行錯誤の身ではありますが、その気持ちが少しずつ分かってきたのです。自信がないのは、実力がないからではなく、むしろ前に進んで努力を続けているから。今はそんなふうに感じています。
本を書くたびに「自信の感じ方」が変わっていった
つい先日、7冊目の電子書籍を出版しおえました。これまでで一番時間がかかり、いちばん悩んだ一冊でした。
書きながら何度も「こんな文章でいいのだろうか」「読者は楽しんでくれるだろうか」と問いが浮かび、すべて書き終えたあとに構成を練り直すことになったほどです。
つまり、書いたものに自信が持てるまでに、少し時間がかかってしまったのです。
思えば1冊目、2冊…3冊目くらいまでは純粋に「書くことが楽しい」という気持ちが強かった気がします。いや、今も書くこと自体はとても楽しくて「どんな本になるだろう」とワクワクしますが、それだけでは済まない気持ちも増えてきました。
私はネガティブな感情が湧いたときは、それを掘り下げるようにしています。
「なんでこんなに書くことに悩むのだろう」と掘り下げて気づいたのは、書くことを続けるうちに見える世界が広がり、目指す場所も少しずつ高くなっているということでした。
だから、以前より自信を感じにくくなっていたのです。
ちゃんと自分に向き合っている証拠なのだと思えたとき、これは喜んでいいことなんだと感じられて、迷いは前向きながんばりに変わりました。
停滞しているときは、むしろ迷いは生まれにくい
人は、まだ見えていなかった景色が見えるようになると、自分の立ち位置をあらためて意識します。前より遠くまで見えるようになった分、「まだこんなに道があるんだ」と実感してしまう。
停滞しているときは、むしろ迷いは生まれにくいものです。
前に進んでいるからこそ、比べる基準が増え、求める未来も少しずつ大きくなり、自信が追いつかなくなる瞬間が出てきます。
さらに、成長には「基準が更新される」という側面があります。昨日までの自分を越えた瞬間に、今日の自分はまた少し先を見ようとする。その前向きさゆえに、いまの状態が物足りなく見えることさえあるのです。
大きくなった視野に心が馴染むまでには時間がかかりますが、やがてまた自然に「できる」と感じられる時期が戻ってくる。その流れを知っているだけで、自信の変化に振り回されにくくなる気がします。
これは「ダニング=クルーガー効果」と呼ばれるもの
心理学には「ダニング=クルーガー効果」という、少し面白い視点があります。
難しそうに聞こえますが、本質はとてもシンプルで、自分の実力をどう感じるかという「心のクセ」を示したものです。
経験が浅いときは、自分の知らない領域に気づいていないため、「意外とできるかも」と自信が大きく育ちます。こうした、まだ届いていない場所に気づいていない時期には、どこへでも進めるような軽やかさがあって、私はその自由さが好きです。挑戦の扉がいくつも開いている感じがするから。
けれど、経験を積むほど世界の広さや深さが見えてきて、「私なんてまだまだだ」と自分を低く見積もりやすくなります。実力は伸びているのに、自信だけが縮んだように感じるのはこのタイミングです。
だから「最近、なんだか自信がない」と思うことがあっても、それは実力不足のサインではまったくなく、むしろ新しい段階に立って、いま目の前の景色を見直しているだけ。
自信は、前へ進んでいる人ほど形が変わりやすいものだと思います。
次のステージへ向かうために必要なプロセス
日々の中で「なんだか今は自信がない」と感じることがあっても、それは自分を根っこから支えている揺るぎない自信そのものがなくなったわけではないのだと思います。
揺るぎない自信というのは、「私ならできる」「私なら大丈夫」「私は進んでいい」と思えることです。これは、経験と積み重ねのなかで静かに育っていくもので、ちょっとしたことで失われるようなものではありません。
新しい景色に触れたときにふっと生まれる不安や戸惑いは、その軸とは別のところで起きるものです。
むしろ、揺るぎない自信という土台があるからこそ、「こういうことも試してみよう」と挑戦でき、その先で自信の感じ方に変化が起きること自体が、次のステージへ向かうために必要なプロセスなのだと思います。