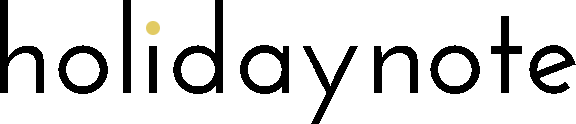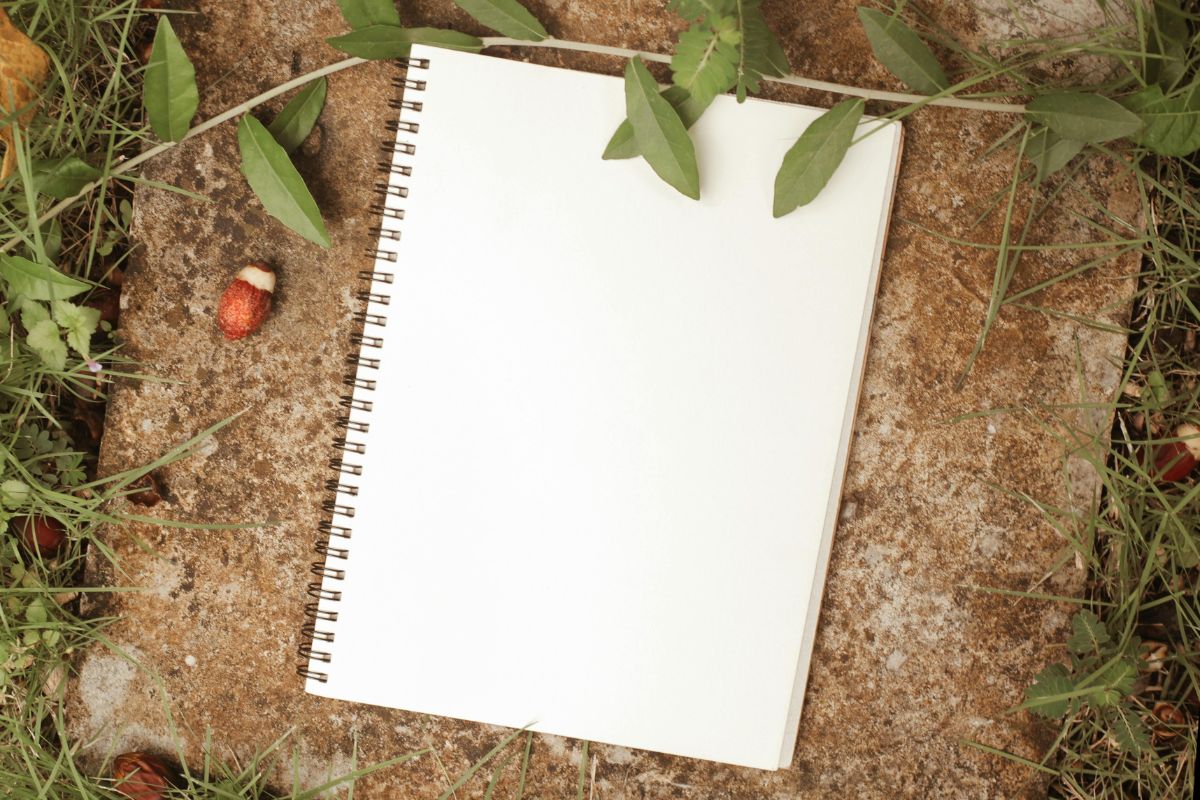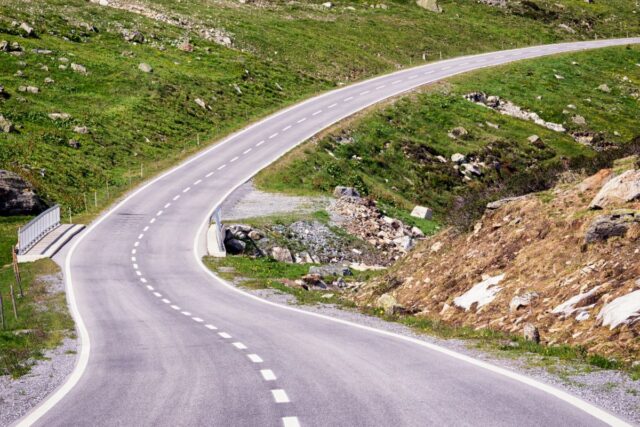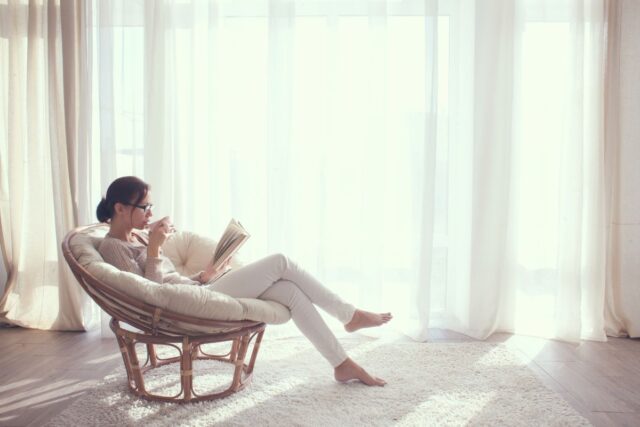出かけた先のカフェでノートを広げて、あれやこれやと仕事のことやアイデアを考えることが多いです。
これまでは、あまり荷物を重たくしたくなかったり、バッグにすっと入るサイズがよかったりして、B6か、少し大きめのA5サイズを選ぶことがほとんど。
さらに小さなバッグの日は、A6サイズを持ち歩きます。
しかし先日、新しいノートを買おうと無印良品へ行き、ふと「大きなノートのほうが発想が広がるかも!」「そういえば、昔、誰かがそんなこと言ってた気がするな〜!」と、大きなノートを買ってみました。
そうしたら見事に、思考の自由度がぐんと広がり、書いているだけでなんだかワクワクしてきたのです。
相変わらず、お出かけ用にはB6サイズが多いですが、家でじっくり考えごとをするときは、大きな無地ノートを広げるのがすっかり定番になりました。
無地のノートは制約がなく自由
罫線のあるノートには、きちんと文字をそろえて書ける安心感があります。
しかし、無意識のうちに「線からはみ出さないように」「きれいに書かなくちゃ」という小さな制約を背負ってしまっている気がします。
その結果、発想もどこか窮屈になってしまいます。
その点、無地のノートはまっさらなキャンバス!
字の大きさも自由なら、文字だけでなく絵を描いてもいいし、真ん中に丸を描いてそこから矢印を伸ばしてもいい。ときには大きな文字をドーンと書いて、そのまわりにアイデアを散りばめていったり。
ページにルールがないからこそ、頭にポンと思い浮かんだままに、書いたり描いたりしながら考えを広げていけるのです。
余計なことにとらわれず、スラスラ手が進み、頭の中で言葉になりきれていなかったものがポンポン生まれてくる感じがします。
大きいノートは思考を制限しない
きっと私だけではないと思うのですが、小さめのノートを使っていて、1ページを書き終えたあとに「まだもう少し書きたいな」と思っても、新しいページをめくるのをためらってしまうことがあります。
その瞬間、書く勢いが途切れ、アイデアを深掘りする前に思考が止まってしまうのです。
さらに、小さなノートだと、まだ半分くらいしか埋まっていなくても、「もうすぐ埋まっちゃうなぁ」と無意識に感じてしまい、そっちに気を取られてしまったり。
その点、大きなノートはページに余裕があります。
広々とした余白が目に入るので、自然と「もっと書き込める」という気持ちになり、遠慮なく思いついたことを書き出せます。
書きたいことがふっと浮かんだ瞬間に、スペースが足りないと感じると、人はそこでブレーキをかけてしまいます。けれど、余白がたっぷりある大きなノートを前にすると、心にもゆとりが生まれます。
思考が途中で立ち止まらず、のびのびと広がっていくように感じています。
大きいノートだと発想が広がる仕組み
大きなノートは、思考を制限しないどころか、余白の広さそのものが発想を引き出す装置になります。
これは、人がもつ“余白を埋めたくなる心理”が働いているのではないでしょうか。
たとえば、ぬり絵で一カ所だけ塗られていないと、なんだかムズムズしませんか?その状態を想像してみても、一カ所だけ真っ白だと、塗りたくなってしまいますよね。
街を歩いていても、文字や写真がぎっしり詰まったポスターより、大きな白い余白のあるポスターや看板のほうが、思わず目を引かれることがあります。
余白があることで、私たちは「ここにはどんな意味があるのだろう」「何が隠されているのだろう」と無意識に考え、ポスターのメッセージにより深く引き込まれるのです。
余白は、ただの空間ではなく、受け手の想像力と集中力を引き出す力をもっているのです。
ノートも同じです。
広い余白のあるページは、まだ何も書かれていない空間が目に入り、「ここを埋めたい」という気持ちをそっと刺激します。
大きいノートのほうが余白が広いぶん、小さいノートよりもその傾向は強まります。
「これ以上書くことがない」と思っても、余白を埋めたくなるから、手を動かしてしまいます。右上に大きな余白あると、そこになにかを書きたくなったり。
それが、発想を引き出してくれるのです。
大きいノートはジャーナリングにも◎
考えごとやアイデア出しだけでなく、ジャーナリングにも大きなノートがぴったり。
ジャーナリングは、そのときの気持ちや考えを思いつくままに書き出すことで、心を整理したり新しい気づきを得たりする習慣です。
広いページには「まだ書ける」という安心感があり、気持ちが途切れにくくなります。小さなノートのようにすぐページをめくらなくていいので、流れるように手を動かせるのも魅力です。
さらに、1ページの中に感情を書き出し、気づきを別の場所にメモしたり、図や矢印を描いたりと、自由度が高いのもポイント。
余白が多いことで、心の中のもやもやを俯瞰して整理しやすくなります。