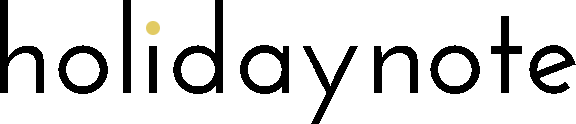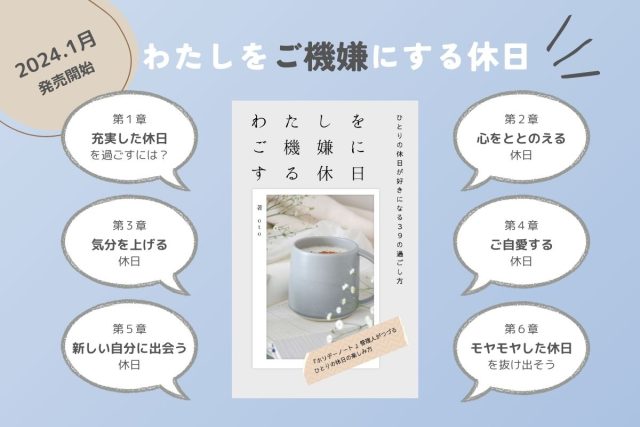鎌倉には苔の石段で知られる「杉本寺」がありますが、もうひとつ、”鎌倉の苔寺”と呼ばれるお寺があります。それが、「妙法寺」です。
暑い夏や寒い冬は土日祝のみの拝観となり、私は夏が終わるのを待って、平日に訪れました。
大町にひっそりと佇む「妙法寺」へ

鎌倉駅からは距離にして約1.3キロ、徒歩18分ほどの場所。大町の松葉ヶ谷と呼ばれる緑豊かな谷あいにひっそりと「妙法寺」は佇んでいます。
鎌倉駅の近くには「妙本寺」というお寺もあり、間違いやすいですが、こちらは「妙法寺」です。
大町のあたりは、駅から離れるほど、観光地じゃない鎌倉の雰囲気が味わえて、つい地元の人になった気分で歩いてしまいます。

受付で拝観料の300円を納めると、お線香をいただけます。白檀の香りが心地いい、火がつけられたお線香を持って本堂へお参り。
本堂がたくさんの植物に囲まれているのが印象的です。

本堂に向かって右手には、境内の奥へと続く細い石畳の道があります。季節の花に彩られ華やかで、私が訪れたときは、フヨウや萩、彼岸花が秋のはじまりを告げていました。

振り返ると、こんな感じ。右側に見えるのが本堂です。そして、手前に見えるのは寺務所などです。

細い石畳を植物たちに囲まれながら歩いていくと、石段の上に朱色の「仁王門」が佇んでいます。仁王門も緑に包まれています。

じゃーん、仁王門です。門の先に、苔むす石段が続くのが見えて、ワクワクしてきます。

さらに近づいてみると、まるで仁王門を額縁にしたような、苔の石段を眺めることができます。
いよいよ苔むす石段とご対面

仁王門はくぐることができないので、左側から回って、いよいよ苔むす石段とご対面!すぐそばには石碑が立っています。

神秘的な雰囲気で、思わず見入ってしまいます。

苔の保護のため、苔むす石段にはのぼれないので、脇にある階段をのぼっていきます。

階段をのぼりながら、苔むす石段を眺める景色もまた美しい。赤い彼岸花が咲いているのもよく見えます。

階段をのぼりきると、落ち着いた木造の「法華堂」が佇んでいます。緑に抱かれた姿が静寂を感じさせます。中には、中興開山の日叡上人作の「厄除祖師」が安置されています。

仁王門を見下ろすように、苔むす石段を上から眺めることができます。下から見上げるのとはまた違った趣です。

鐘楼も緑に包まれています。鐘楼のすぐ近くには階段があり、さらにのぼります。

だんだん見晴らしがよくなってきます。赤い彼岸花が彩りを添えていてきれいです。

階段をのぼった先には「松葉谷御小庵跡」があります。ここは、日蓮聖人が鎌倉で最初に草庵を結んだ場所と伝えられているところ(諸説あります)。文応元年(1260)、この地で『立正安国論』を著し、北条時頼に提出したのだそうです。その主張が反感を呼び、同じ年の8月に起きた「松葉谷法難」で焼き討ちされてしまいました。
今では当時の草庵は残っておらず、石碑と小さな祠が静かに建っています。
山道をのぼった先に海を望む景色が!

ここからさらに上へとのぼります。「護良親王御墓」と書かれていなければ、のぼっていいのかどうかもわからない、狭い石段がつづく山道です。

ひたすらのぼっていきます。

ようやく、「大塔宮供養塔」がありました。ここは、後醍醐天皇の皇子・護良親王(大塔宮)を供養するために建てられた塔です。
護良親王は鎌倉幕府を倒すために尽力しましたが、その後の建武政権の内紛で足利尊氏に鎌倉でとらえられ、命を落とした悲しい歴史があります。

そして、たくさんのぼってきたご褒美とばかりに、豊かな緑に囲まれた高台からは、木々の合間から鎌倉の街並みと相模湾を遠くに望むことができます。お寺の方によれば、葉っぱがない冬のほうが、海がさらによく見えるそうです。
静寂に満ちていて心が落ち着くお寺

鎌倉の妙法寺は、本堂周辺は花や草木に包まれていて穏やかな雰囲気ですが、奥へ進み、さらに上へとのぼっていくほど、驚くほど深い静寂に包まれていきます。
足を進めるごとに、人の気配も遠のいていき、心もすーっと落ち着きます。そして、最後に眺める相模湾の景色は、がんばったご褒美のような景色!
天気によっては富士山も見えるそうなので、また訪れたいと思います。
住所・アクセス/関連サイト
神奈川県鎌倉市大町4-7-4
「鎌倉駅」より徒歩18分