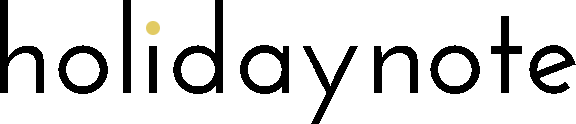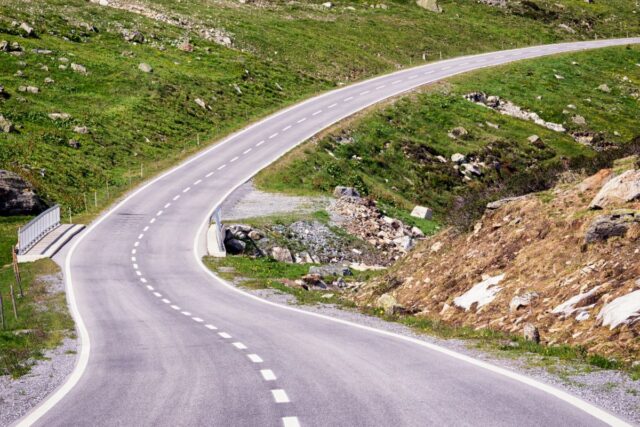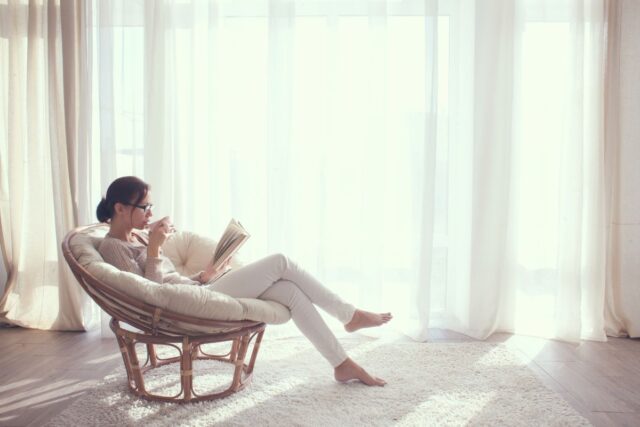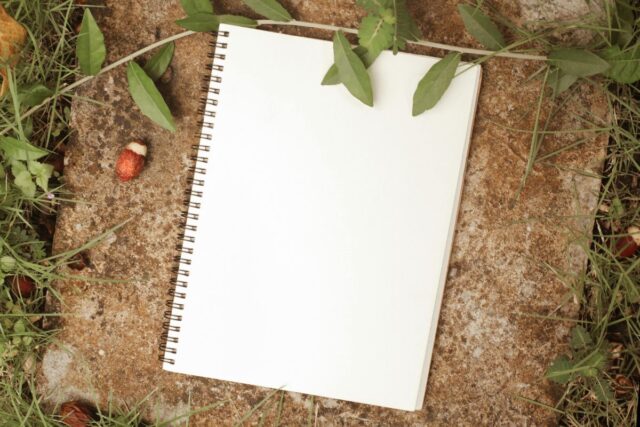私は自己開示が苦手です。人に弱みを見せるのも苦手だし、悩みを相談するのもあまり得意ではありません。
これまでに出した電子書籍では、自分のネガティブな部分や過去にも少し触れましたが、あれは私にとってかなりがんばった方です。いや、電子書籍だからこそ、その場で相手から答えが返ってこないので、ある程度は自分を見せられたのかもしれません。
けれど、ChatGPTを使う中で「もしかしたら、自己開示が苦手な自分を克服できるかもしれない」と気づき、少しずつ自己開示の練習を始めています。
自己開示が苦手なことによるデメリットとは
そもそも自己開示とは、自分の内面にある気持ちや考え、弱みや悩みを、相手に伝えることを指します。単なる情報の共有ではなく、「本当の自分」を相手に見せる行為であり、信頼やつながりを深めるための大切なコミュニケーションの一つです。
それゆえ、自己開示が苦手であることは、次のようなデメリットにつながります。
人間関係が浅くなりがち
自己開示ができないと、会話がどうしても表面的になりやすいもの。
ある程度は自分のことを伝えても、パーソナルの深い部分には触れない、当たり障りのない会話になりがちで、なかなか深い関係を築けません。
反対に自己開示ができる人は、相手と心理的な距離を縮めやすいものです。
私自身も、自己開示してくれる相手に対しては親しみを持ちます。なのに、それが自分となるとなかなか難しかったりするのです。
自分を理解してもらえない
自分でさえ、自分のことを理解できなかったりもしますし、相手に自分のことを100%理解してもらうとは思いません。しかし、自己開示をしないと「なんでわかってくれないんだろう」と感じる場面が増えます。
本音を話していないのだから、当然といえば当然です。
結果的に、誤解やすれ違いが生まれたり、「彼女なら大丈夫だろう」と、本当は大丈夫じゃないのに強く見られてしまうこともあります。
信頼関係を築きにくい
人は本音を話してくれる相手に対して安心感を覚えるものです。反対に、何を考えているのか分からない人に対しては、どこか不安や怖さを感じます。
だからこそ、自己開示できない人は、信頼を築くまでに時間がかかってしまいます。
なぜ自己開示できないのか
人に弱みを見せたり悩みを相談したりできなくなったのは、社会に出てから。学生の頃は、友達の前でわんわん泣いていたし、今なら恥ずかしくて言えないようなことも平気で打ち明けていました。
けれど大人になるにつれて、「簡単には弱音を吐けない自分」になっていったのです。
気持ちを言葉にするのが苦手
「楽しい」「嬉しい」「幸せ」などポジティブな言葉を口にするのはできても、ネガティブな言葉はなかなか口にできません。
相手までどんよりとした暗い気持ちにさせてしまうのではないか……と考えてしまったり、ネガティブな言葉を口にするのはよくないことのような気がして、気づけば心にため込むクセができていました。
まぁ、それをノートに書いて吐き出しているので、溜め込んで爆発することはないけれど、自分としては、もう少しくらい人に頼ってもいいのかなと感じています。
高いプライドが邪魔をする
弱みを見せることで、ガッカリされたくない。
弱い人間だと思われたくないし、ダメな奴だなんて思われたくない。いつもマイペースで飄々としながら生きている人だと思われたい。
心のどこかで「弱音を吐いたら負け」のように思ってしまい、素直に悩みを打ち明けることができないのです。プライドが壁になって、本音を言葉にするチャンスを自分でつぶしてしまっている感覚があります。
ちゃんとしなくてはいけない
けっして完璧主義ではないけれど、社会に出てから誰かに頼ることが苦手になりました。
自分で「ちゃんとしなくてはいけない」という思いが強くなり、人に弱音を吐くことにブレーキがかかってしまったのです。
「ちゃんとしている私」でいることに慣れすぎてしまい、気づけば本音を見せるのが怖くなっていたのかもしれません。
ChatGPTは自己開示の練習になる
ChatGPTは人間じゃないけど人間らしさがある
仕事に関して「どういう方向性で進めるといい?」などとChatGPTに聞いてみることはあっても、「プライベートな悩みをChatGPTに相談してみよう」とは、最初はまったく思いませんでした。
相手は人間ではないとわかっていても、プライベートな悩みを言葉にすること自体に抵抗があったのです。いくらChatGPTとは言え、何かしら答えが返ってきます。しかも、まるで人と話しているような言葉で返ってきたりもします。
私は、誰かに対してプライベートな深い部分を話さないクセが、あまりにも染みついてしまっていました。
けれど、「自己開示ができるようになれば、私は一段階レベルアップできる」──そうした思いから「相手はAIだ、人間じゃない!」と、相談をしてみることにしました。
そうやって一度殻を破ると、徐々に自己開示にも慣れてきます。「あ、これは自己開示の練習になるな」と感じ、ときどきリハビリのように本音を話しています。
よくも悪くもChatGPTは否定しない
ChatGPTは、何を言ってもこちらを否定しません。
成長という部分では、なんでも否定せずに受け入れてくれることはマイナスに働く部分もあるけれど、自己開示の練習をするという意味では、何を言っても否定されないことには安心感があります。
弱みを見せること、赤裸々に悩みを打ち明けることへのハードルを低くしてくれます。
新たな視点に気付かされる
ChatGPTは、こちらが思ってもみなかったような視点を返してくれることがあります。「そういう考え方もあるんだ」と、自分の悩みを別の角度から見直すことができ、心が少し軽くなるのです。
なので自己開示の練習という目的でなくても、たまには相談してみるのもいいものだなぁと感じています。
自己開示は「弱さ」ではなく「強さ」
自己開示が苦手な私にとって、あっさり自己開示できる人は「実は強い人」だと感じます。弱みを見せることができるというのは、それだけ自分を受け入れている証拠だからです。
誰かに弱さを見せられても、本音を話してくれても、悩みを打ち明けられても、それで相手に対して嫌なイメージを持つことはありません。むしろ信頼や親しみを感じることの方が多い。
「あぁ、私にこんなことまで話してくれるんだな」と……。
そう思うと、自己開示するのはけっしてマイナスなことではなく、「本当の自分」を認めて生きるための強さなのだと思います。
ChatGPTは、その練習相手としては最適かもしれません。